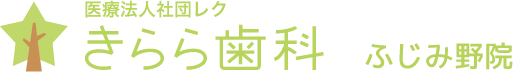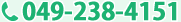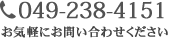きらら通信
きらら通信3月号
こんにちは! 医療法人レクきらら歯科です!
医療法人レクでは毎月「きらら通信」 を発行しています
3月は『お口の老化サイン』についてです。
詳しく知りたい方はお気軽にスタッフにお声かけください!
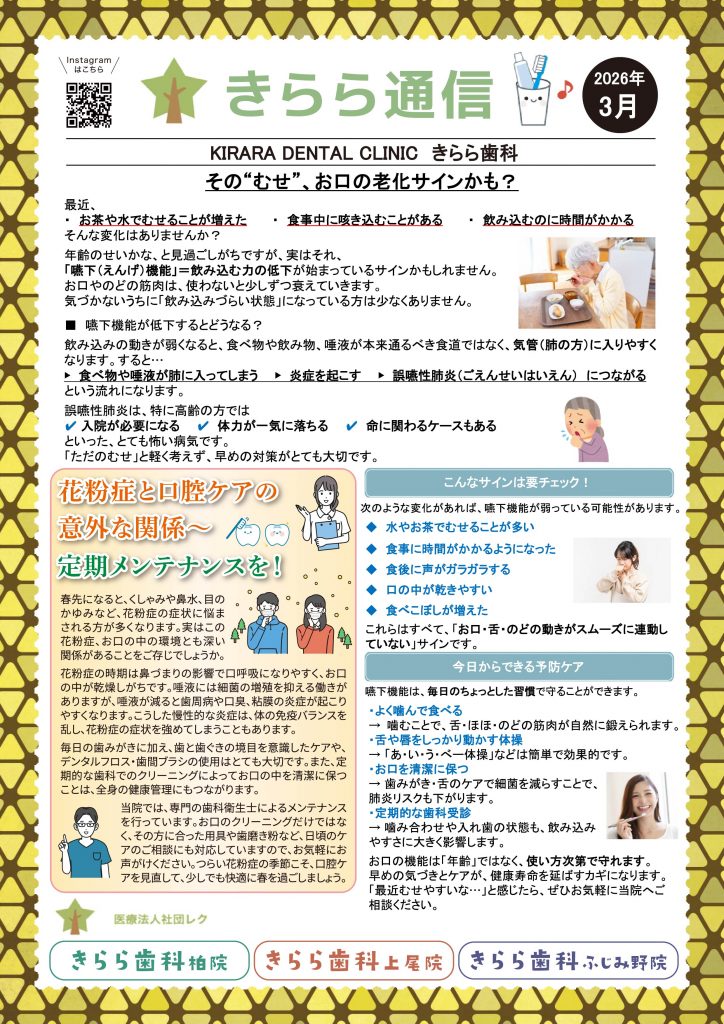
今日から始める潤い習慣 唾液を守る生活の工夫
こんにちは。
ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。
今回は、日常生活の中で意識したい「お口の潤いケア」についてご紹介します。お口の乾燥は、冬場など季節の影響によるものと思われがちですが、実際には普段の生活習慣が大きく関係しています。唾液の分泌は、日々の行動や癖によって左右されるため、少し意識を変えることで乾燥対策につなげることができます。
口腔乾燥と生活習慣の関係
現代の食生活は柔らかい食品が多く、噛む回数が自然と減りがちです。また、会話の機会が少ない生活スタイルも、唾液腺への刺激不足につながります。その結果、唾液の分泌量が低下し、お口の乾燥を感じやすくなります。唾液はお口を潤すだけでなく、細菌の増殖を抑え、粘膜を守る重要な働きをしています。
噛むことがもたらす効果
噛むという行為は、唾液腺を活性化させる最も自然な刺激です。食事の際によく噛むことはもちろん、食後や口の渇きを感じたときにガムを噛む習慣も有効です。噛むことで唾液が分泌され、お口の中が潤いやすくなり、清潔な環境を保つ助けとなります。
水分補給の工夫
水分補給は、のどの渇きを感じてから行うのではなく、こまめに摂ることが理想的です。特に空調の効いた室内では、知らないうちに体内の水分が失われがちです。糖分を多く含むジュースや清涼飲料水よりも、水やお茶を選ぶことで、お口の乾燥対策につながります。
唾液腺マッサージと舌の運動
ほほや耳の下、あごの下をやさしく刺激する唾液腺マッサージや、舌を上下左右に大きく動かす体操は、唾液分泌を支える簡単な方法です。短時間でも毎日続けることで、唾液腺の働きをサポートできます。
鼻呼吸の重要性
無意識の口呼吸は、お口の中を乾燥させやすく、むし歯や歯周病、口臭の原因となることがあります。普段から鼻呼吸を意識することで、口腔内の潤いを保ちやすくなります。就寝中の口呼吸が気になる場合は、歯科医院に相談するのも一つの方法です。
乾燥を軽視しない
お口の乾燥を放置すると、むし歯や歯周病、口臭だけでなく、食べ物が飲み込みにくい、話しづらいといった症状が現れることがあります。特に高齢者では、誤嚥など全身の健康への影響も無視できません。
まとめ
お口の乾燥は、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。唾液の大切な役割を理解し、噛む・飲む・呼吸といった日常の小さな意識を積み重ねることで、お口の健康を守る第一歩としましょう。
冬は要注意 唾液の減少が引き起こすお口の変化
こんにちは。
ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。
今回は、冬に起こりやすいお口の乾燥と唾液の働きについてご紹介します。1月を中心とした冬の時期は、湿度が大きく下がり、空気が乾燥しやすくなります。さらに暖房の使用により室内の湿度も低下し、体全体の水分が奪われやすい環境が続きます。その影響は肌や喉だけでなく、お口の中にも及び、唾液の分泌量が減少しやすくなります。その結果、「口の中が渇く」「ネバつく」「話しづらい」といった違和感を覚え、ドライマウスと呼ばれる状態を自覚する方が増えてくるのが冬の特徴です。
唾液が持つ多面的な役割
唾液は、単にお口を潤すための水分ではありません。むし歯菌や歯周病菌の増殖を抑える抗菌作用を持ち、口腔内の細菌バランスを整える重要な役割を担っています。お口の中には常に多くの細菌が存在していますが、唾液が十分に分泌されていることで、細菌が過剰に増えにくい環境が保たれています。また、食事の後に残った食べかすや汚れを洗い流す「自浄作用」も唾液の大切な働きのひとつです。これにより、歯や歯ぐきへの負担が軽減され、トラブルが起こりにくい状態が維持されています。
粘膜の保護と口腔トラブル
唾液は、お口の中の粘膜を潤し、乾燥や外部からの刺激から守るクッションのような役割も果たしています。粘膜が適度に潤っていることで、食事や会話による摩擦の影響を受けにくくなります。しかし、唾液の分泌が低下すると粘膜が乾燥し、わずかな刺激でも傷つきやすい状態になります。その結果、口内炎ができやすくなったり、ヒリヒリとした不快感が続いたりすることがあります。冬に口の中の痛みや違和感を訴える方が増える背景には、このように唾液量の変化が関係しています。
噛む・飲み込む・話すへの影響
唾液は、噛んだ食べ物をまとめて飲み込みやすくする働きや、発音を滑らかにする働きにも深く関わっています。唾液が十分に分泌されていることで、食事中に食べ物がスムーズに喉へ運ばれ、会話も自然に行うことができます。一方、唾液が不足すると、食べ物が口の中でまとまりにくくなり、飲み込みづらさを感じることがあります。また、口が渇いて話しにくくなり、人との会話が負担に感じられることもあります。これらは日常生活の快適さに直結する問題です。
口臭や味覚低下との関係
唾液が減少すると、お口の中で細菌が増殖しやすくなり、口臭が強くなる傾向があります。唾液には口臭の原因となる物質を洗い流す働きがあるため、その量が減ることで臭いがこもりやすくなるのです。また、味覚を感じるためには、味物質を唾液に溶かす必要があります。そのため、唾液が不足すると「味が分かりにくい」「食事がおいしく感じない」といった変化を感じることもあります。
お口の乾燥が及ぼす広い影響
口腔乾燥は、お口の中だけの問題にとどまらず、食事や会話といった日常生活全体に影響を及ぼします。食べることや話すことが億劫になることで、生活の質が低下してしまうケースも少なくありません。冬の乾燥は、知らないうちにお口の環境に負担をかけている可能性があります。
まとめ
冬の乾燥は、唾液の分泌量を低下させ、お口の環境にさまざまな変化をもたらします。季節によるお口の変化に目を向け、自身の口腔状態を意識しましょう。
きらら通信2月号
こんにちは! 医療法人レクきらら歯科です!
医療法人レクでは毎月「きらら通信」 を発行しています
2月は『家庭内での歯周病感染』についてです。
詳しく知りたい方はお気軽にスタッフにお声かけください!
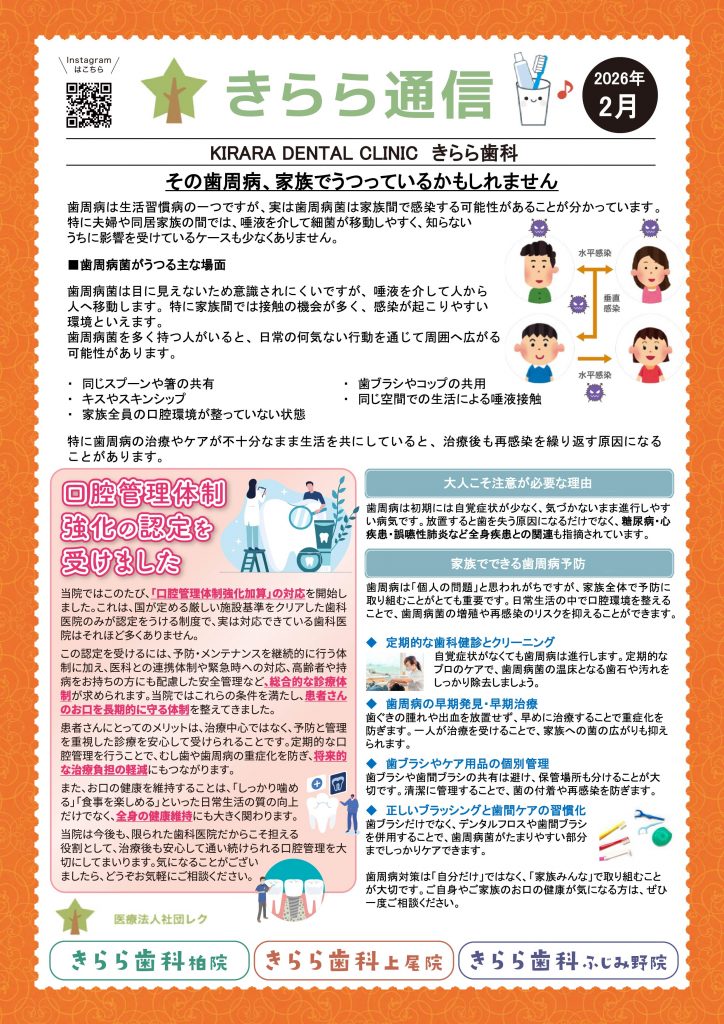
避難先で困らないために 今からできる口腔ケアの備え
こんにちは。
ヤオコーふじみ野大原敷地内の歯医者、きらら歯科ふじみ野院です。
今回は、災害時にそなえる「お口のケアの必需品」についてご紹介します。
災害が起きると、生活のリズムが乱れ、衛生環境も大きく変わってしまいます。特に水や電気が止まると、歯みがきが困難になり、口の中を清潔に保つことが難しくなります。しかし、非常時に口腔ケアを怠ると、お口だけでなく全身の健康にも影響することがあるため、事前の備えがとても大切です。
避難時にお口の健康が損なわれやすい理由
災害時は食事が偏りやすく、口腔内に汚れが溜まりやすい状況が続きます。また、ストレスによって唾液の分泌が減ると、細菌が増殖しやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが高まります。高齢の方では、細菌が増えた唾液が気管に入り込むことで誤嚥性肺炎を引き起こす可能性もあります。
携帯歯ブラシの準備を
災害時には折りたたみ式の歯ブラシが便利です。水が少なくても使用でき、乾いたまま磨いても汚れを落とせるので、最低限の清潔を保つことができます。使い終わったらティッシュで拭き取るだけでOKです。
洗口液で簡単にケア
水を使えない状況で役立つのが口腔用の洗口液です。殺菌作用や保湿機能のある洗口液を選んでおくことで、不快なネバつきや口臭を軽減できます。非常用袋に入れておくと、いつでも使えて安心です。
ウェットティッシュの活用
ノンアルコールタイプのウェットティッシュは、口の周りの清掃や手指の衛生管理にも活用できます。避難生活では衛生用品が限られるため、多用途に使えるウェットティッシュはとても便利なアイテムです。
ミラーと紙コップの意外な重要性
小型のミラーがあると、口の中の状態をしっかり確認できます。紙コップはうがい用としてだけでなく、洗口液を使うときにも便利です。自分の口の状態を把握できることは、災害時のトラブル予防につながります。
ガムや湿潤剤で乾燥対策
唾液が減ると細菌が増えやすくなり、口腔内のトラブルが発生しやすくなります。キシリトールガムは唾液を出す手助けとなり、湿潤剤は口の中を潤すことで快適さを保ってくれます。
まとめ
いつ起こるかわからない災害に備え、口腔ケア用品を非常用持ち出し袋に入れておくことは、健康を守るための大事なステップです。携帯歯ブラシ、洗口液、ウェットティッシュ、ガム、湿潤剤などをひとまとめにしておくことで、避難生活での不安を減らし、清潔な口腔環境を保ちやすくなります。平常時から定期的に内容を見直し、万が一のときにすぐ使えるよう準備しておきましょう。